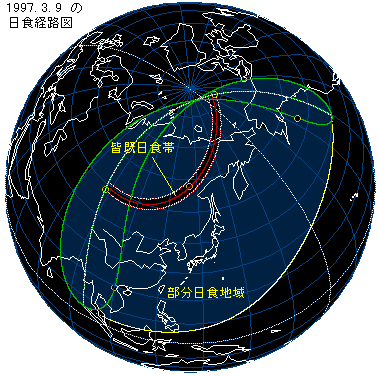
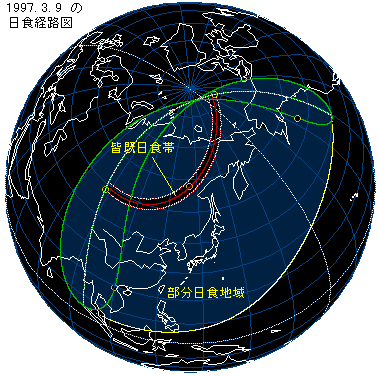
またシベリアやモンゴル付近(右図の中央付近の細い帯)では、皆既日食となります。厳寒の地で黒い太陽を見ようと、日本からも多くのツアー・観測隊が向かう予定です。
国内ではおよそ北に向かうほど食分が大きくなり、稚内では79%にのぼります。関東以西では食分はほぼ同じで、65%前後になります。
(右図は、客星さん作成のフリーソフト「EMAP」に若干手を加えてて作成したものです。なお、作者の客星さん(竹迫忍さん)のホームページ「古天文の世界へようこそ」はこちらです。
また本ソフトは、甲田さんの「古天文学と天文民俗学の部屋」のページの中の、古記録の検証に便利なソフトからダウンロードできます。)
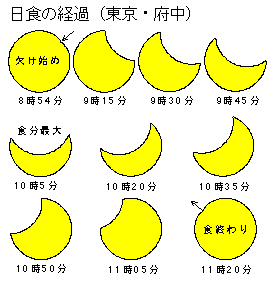
各地でのもう少し詳しい時刻データはこちら。
以下の各地のデータを掲載しています。
なお、普通のサングラス、黒い下敷き、カラーフィルム等は目を痛めますので、絶対に避けましょう。またカメラ用のNDレンズも、熱線を若干通すので避けた方がよいとの話を聞いたことがあります。注意しましょう。

また、墨汁を器に入れて、その水面に太陽を映すとまぶしくなく見えるそうです。1988年に小笠原沖で皆既日食を見たとき、これをしている方がおりました。
なおFAS府中天文同好会では、府中市郷土の森博物館の日食観測会で、一緒に観測しました。
 欠け始め直後
欠け始め直後
 食の最大の頃(食分約0.64)
食の最大の頃(食分約0.64)
 欠け終わり約1分前
欠け終わり約1分前