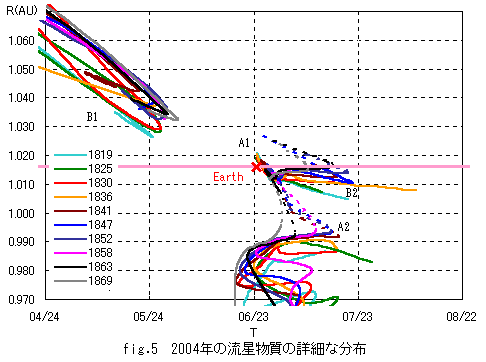Pons-Winnecke彗星由来の流星群の
2004年出現の可能性についての検討
〜中間報告 1〜
現在計算を行っている、2004年に出現の可能性のあるこの流星群についての中間報告です。計算時間が長く今後もまとめるまでに時間がかかると思われるので、まとめた内容まで公開することにしました。
今後も計算ができ次第、徐々に内容を増やしていきたいと思います。
更新履歴
- 2003.12.25 公開開始
- 2004.01.07 近日点通過前・後における放出による分布の検討(1825年放出分)を追加
[母天体概要]
ポン・ウィンネッケ彗星(7P/Comet Pons-Winnecke)は、1819年にフランスの Jean Louis Pons が発見した周期彗星である。その後、1858年にドイツの Friedrich August Theodor Winnecke が発見した彗星が、この彗星の再来だったことが判明し、以降、ポン・ウィンネッケ彗星の名前で呼ばれている(なお、日本語表記については諸説あるが、最も一般的に使用されている「ポン・ウィンネッケ」を使用することとする)。
この彗星が放出した物質による流星群は、過去1916年、1921年、1927年、1998年に大出現を記録している。
この彗星の地球軌道面通過年と、その際の太陽からの距離をfig.1に示す。この彗星の周期は約5〜6年である。1819年の発見以降1869年の回帰までの50年間、非常に軌道が安定していたことがわかる。
その後、ほぼ2回帰毎に木星の摂動を受け、軌道が大きくなり続ける。1921年の回帰以降、地球軌道面通過時の彗星軌道の距離は、地球軌道よりも大きくなり、地球の外側となる。その後1957年の回帰までこの増加傾向は続くことになる。
その後は現在まで、地球軌道の外側で軌道はほぼ安定している。
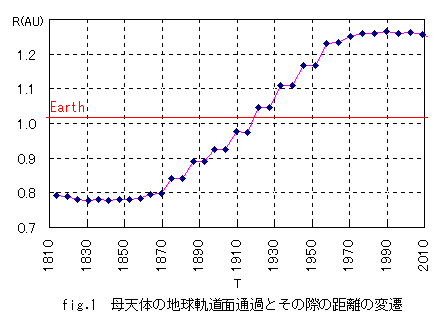
[流星物質分布の概要]
2004年の出現の可能性を検討するにあたり、流星物質の分布を概略計算した結果、前回大出現した1998年と、2004年では、流星物質の分布が非常に似ていることがわかった(詳細はこちらの結果参照)。1998年の分布をfig.2に、2004年の分布をfig.3に示す。なお流星物質の放出条件は+30[m/s]〜-30[m/s]である。
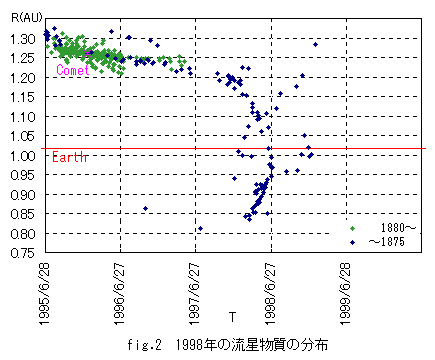
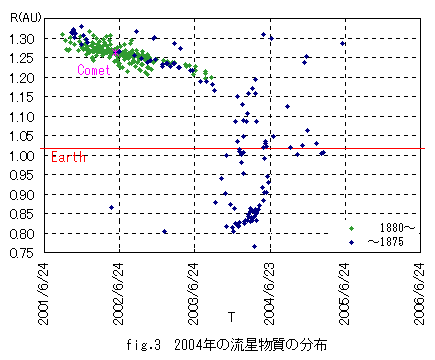
1998年と2004年に共通することは、1819〜1869年の軌道が非常に安定していた時期の流星物質が、彗星本体の回帰よりも少し遅れた時期に、地球軌道付近に回帰することである。概略計算では、この期間および一度だけ木星の摂動の影響を受けた1975年からの物質で、回帰する可能性があることがわかった。
これよりも後の1880年以降に放出された流星物質は、木星の摂動とのかねあいで(今回用いた-30〜+30[m/s]の放出速度では)1998年、2004年とも地球軌道に接近しなかった。
以上をふまえ、さらに詳細計算を進めることとした。
[流星物質の分布の遷移]
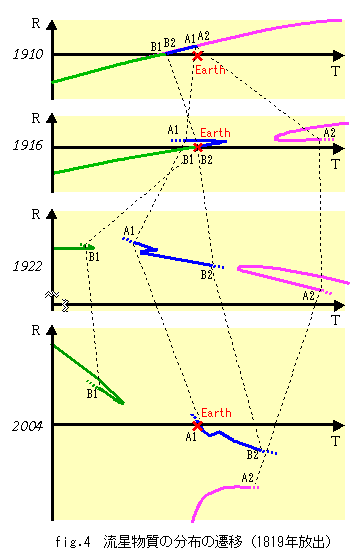 数値積分シミュレーションソフト「NIPE」を用いて、検討した結果、1819〜1841年放出の流星物質が2004年に地球軌道に接近しそうな結果を得た。しかしながら、これらは木星の摂動以外に、1910年および1916年に地球に非常に接近し、その摂動の影響で分布が乱され、途切れ途切れになっていることが判明した。fig.4に1819年放出の物質の分布を例示し、これについて説明する。
数値積分シミュレーションソフト「NIPE」を用いて、検討した結果、1819〜1841年放出の流星物質が2004年に地球軌道に接近しそうな結果を得た。しかしながら、これらは木星の摂動以外に、1910年および1916年に地球に非常に接近し、その摂動の影響で分布が乱され、途切れ途切れになっていることが判明した。fig.4に1819年放出の物質の分布を例示し、これについて説明する。
この部分の流星物質は1910年までは一筋のトレイル状で存在する。まず1910年に地球に接近する。この際、地球通過よりも前(グラフ上A1より左側)で回帰した物質は、地球の重力により減速し軌道が小さくなり、次回の回帰時期が早くなる。逆に地球通過よりも後(グラフ上A2より右側)で回帰した物質は、地球の重力により加速し軌道が大きくなり、回帰時期も遅くなる。この結果、次の回帰である1916年には、流星物質の不連続な部分が生じる(A1/A2)。
さらに流星物質のトレイルは1916年にも地球に接近する。特に1819年放出の帯は、地球軌道と交差し(6/29 22:32UT 距離=0.0006AU)、この年の大出現の原因トレイルとなっている(後述)。この際も、1910年と同様の現象が生じ、次の回帰の際にB1とB2の間に不連続な部分を生じる。
その結果、1922年の回帰時(母天体回帰は1921年)には、不連続な部分で切り取られて取り残された一つの島状の部分(A1〜B2)となる。この部分は、元のトレイルとは前後が反転している。この年以降、この部分は地球と接近することはなく、木星の摂動のみにより変化する。
その後何度か木星の摂動の影響を受け、最終的には2001年に木星に接近し地球軌道に接近するようになる。そして2004年、島状の部分の一番先端(A1)で、地球と遭遇する。
[2004年の流星物質の分布]
1819〜1869年に放出された流星物質の、2004年の分布をfig.5に示す。
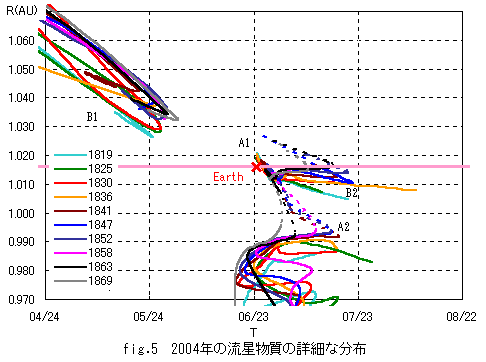
前述の通り、2004年は取り残された島状の部分(A1〜B2)の先端で、地球と接近する。このような島状の傾向は、1910年および1916年における地球との接近距離の小さい1819年放出物質で顕著である。一方で後年に放出された物質になるほど、1910年、1916年とも地球との接近距離が遠くなるため、不連続性が薄くなる。このため、1941年以降の放出物質では、A1とA2が連続するようになり、またB1とB2もやや連続する傾向が見られる。
さらにfig.5の拡大をfig.6に示す。
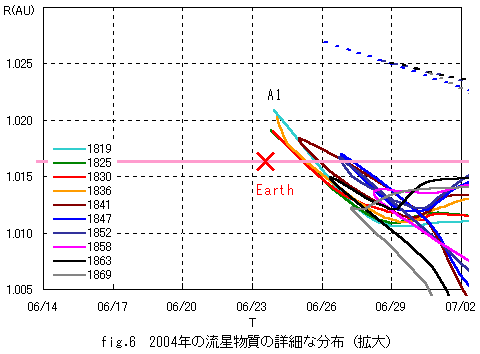
この結果、1819〜1836年放出物質については、A1の部分がおよそ0.003〜0.005[AU]に接近することが判明した。これらは距離が若干大きいが、十分に出現の可能性のある値と判断する。
1841年以降の放出物質は、次第にA1とA2が連続するようになり、その結果、流星物質は地球との接近点までは分布が広がらない。地球軌道に達するのは、地球が通過後数日経過した後となる。しかしながら、分布の広がりの大きさによっては、2004年の出現に関与する可能性がある結果といえる。
後半のページへ 流星ノートに戻る
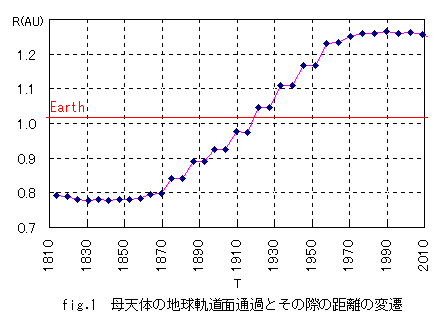
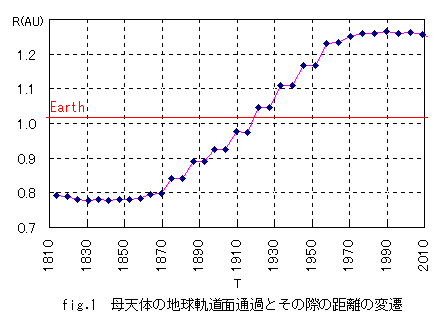
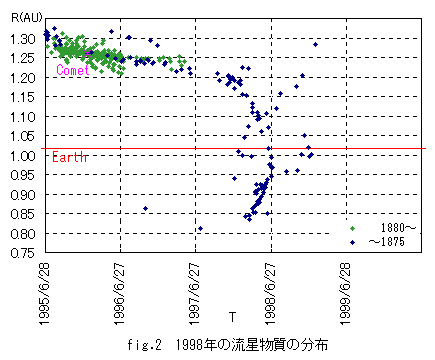
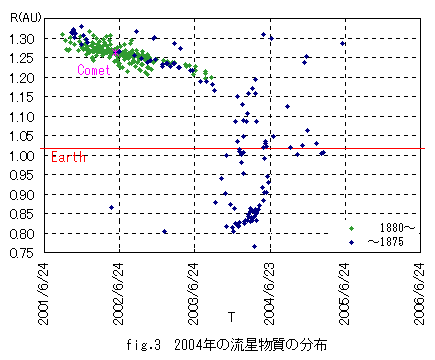
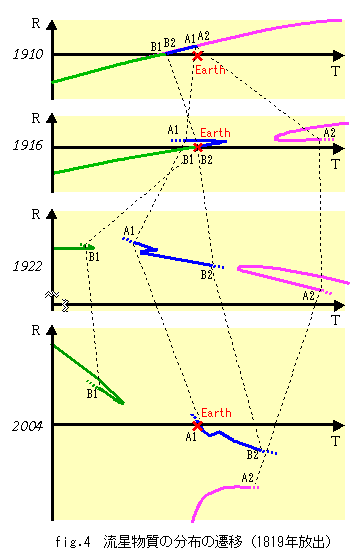 数値積分シミュレーションソフト「NIPE」を用いて、検討した結果、1819〜1841年放出の流星物質が2004年に地球軌道に接近しそうな結果を得た。しかしながら、これらは木星の摂動以外に、1910年および1916年に地球に非常に接近し、その摂動の影響で分布が乱され、途切れ途切れになっていることが判明した。fig.4に1819年放出の物質の分布を例示し、これについて説明する。
数値積分シミュレーションソフト「NIPE」を用いて、検討した結果、1819〜1841年放出の流星物質が2004年に地球軌道に接近しそうな結果を得た。しかしながら、これらは木星の摂動以外に、1910年および1916年に地球に非常に接近し、その摂動の影響で分布が乱され、途切れ途切れになっていることが判明した。fig.4に1819年放出の物質の分布を例示し、これについて説明する。