SL-9衝突痕の時間変化 田部 一志

 観測されたSL-9衝突痕の形状変化から、衝突痕の発生した緯度、特に高緯度に注目して、その緯度における風速を予測したもの。おまけで、1690年にあのカッシーニ(カッシーニの空隙で有名)のスケッチ(右図)に描かれた黒い斑点が、SL-9の衝突痕の変化に似ていると言うことを紹介されました。
観測されたSL-9衝突痕の形状変化から、衝突痕の発生した緯度、特に高緯度に注目して、その緯度における風速を予測したもの。おまけで、1690年にあのカッシーニ(カッシーニの空隙で有名)のスケッチ(右図)に描かれた黒い斑点が、SL-9の衝突痕の変化に似ていると言うことを紹介されました。
南温帯縞(STB)と永続白斑 伊賀 祐一

 今シーズンを中心に、南温帯縞の形状と、この緯度に見られた永続白斑等の模様について発表されました。特に永続白斑とその他の白斑の関係について、渦の方向などをもとに考察されました(右図)。
今シーズンを中心に、南温帯縞の形状と、この緯度に見られた永続白斑等の模様について発表されました。特に永続白斑とその他の白斑の関係について、渦の方向などをもとに考察されました(右図)。
今年発生した土星の暗斑について 浅田 秀人
 この夏に土星面に発生した暗斑について発表されました。土星面の風速の差が木星面のそれに比べて大きいことから、これはFestoon(フェストーン)が横に伸びて見られてるものではないかと考察されました。
この夏に土星面に発生した暗斑について発表されました。土星面の風速の差が木星面のそれに比べて大きいことから、これはFestoon(フェストーン)が横に伸びて見られてるものではないかと考察されました。
木星経年変化 1972〜1996 安達 誠


25年間の各年(1981年を除く)における、特徴的な木星面のスケッチを1枚ずつまとめたものが配布されました。解説もあり、貴重な資料であります。
次回の開催地について
安達さんから来年京都で行われるIAUの時期に合わせて京都で行うことを提案され、了承されました。この際、田部さんと長谷川さんが、IAUに来られる海外の研究者とコンタクトをとり、講演を行って頂く方向で調整することとなりました。
簡単な感想
今年怪鳥は発表もなく、また観測データもあまりない状態でしたので、ほとんど参加するだけと言った状態になってしまいましたが、皆さんの発表を聞くことで非常に刺激を受けて来ました。来シーズンは、観測をもっと頑張りたいものであります。
集合写真・その他のスナップなどはこちら
(画像中心のため、アクセスに時間がかかる可能性あります。ご注意下さい)
さらに詳しい報告は、月惑星研究会関西支部の中の「木星観測者会議 報告書」をご覧下さい。
 今年の世話人は、富山県天文学会の渡辺康充さん。富山大を卒業し、木星観測者会議初の富山での開催を実行されました。お疲れさまです。
今年の世話人は、富山県天文学会の渡辺康充さん。富山大を卒業し、木星観測者会議初の富山での開催を実行されました。お疲れさまです。 安達 誠さんが司会となって、今シーズンの木星面の模様について、報告とまとめが行われました。関東と関西の眼視・写真・CCD観測者がデータを持ち寄り、白熱した議論が交わされました。1日目では終わりきらず、2日目の始めまでかかりました。
安達 誠さんが司会となって、今シーズンの木星面の模様について、報告とまとめが行われました。関東と関西の眼視・写真・CCD観測者がデータを持ち寄り、白熱した議論が交わされました。1日目では終わりきらず、2日目の始めまでかかりました。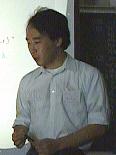 Albedo(反射能)を観測から求めることで、木星面の明るさを定量的に調べようというものです。1996年8月25日の観測の概要も紹介されました。
Albedo(反射能)を観測から求めることで、木星面の明るさを定量的に調べようというものです。1996年8月25日の観測の概要も紹介されました。

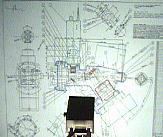 CCDが普及し、アマチュアレベルでも分光器を自作するだけで、吸収線を観測することが出来るというもの。望遠鏡は28cmシュミカセ、CCDはST-6を使用し、分光器は約20万で自作。NH3やCH4の吸収線の実測が紹介されました。
CCDが普及し、アマチュアレベルでも分光器を自作するだけで、吸収線を観測することが出来るというもの。望遠鏡は28cmシュミカセ、CCDはST-6を使用し、分光器は約20万で自作。NH3やCH4の吸収線の実測が紹介されました。 岡山の188cmによるSL-9の衝突痕跡の明るさの変化を発表されました。94年7月(衝突直後)、95年4月・5月(10ヵ月後)、96年7月(2年後)の明るさの違いから、分布する物質の空間密度をシミュレーションされました。
岡山の188cmによるSL-9の衝突痕跡の明るさの変化を発表されました。94年7月(衝突直後)、95年4月・5月(10ヵ月後)、96年7月(2年後)の明るさの違いから、分布する物質の空間密度をシミュレーションされました。