この原稿は、府中市郷土の森博物館星空観測会(7.27、8.3)で配布する予定だった資料の転載です。
夏は「ながれぼし」、すなわち「流星」が多く見られる季節です。その中でも「ペルセウス座流星群」(通称「ペルセ群」)が見られる8月11〜13日の晩は、ひときわ多く流れるので、チャンスです。
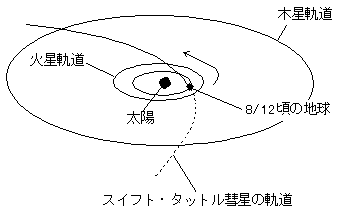 流星の正体は、彗星(ほうき星)が太陽に近づいたときに、熱で溶けて放出した塵(ちり)だと言われてます。これがたまたま地球に飛び込んできたとき、大気との摩擦で高熱になって光を放ち、流星として私たちの目にきれいな姿を見せるのです。
流星の正体は、彗星(ほうき星)が太陽に近づいたときに、熱で溶けて放出した塵(ちり)だと言われてます。これがたまたま地球に飛び込んできたとき、大気との摩擦で高熱になって光を放ち、流星として私たちの目にきれいな姿を見せるのです。
ペルセ群は、スイフト・タットル彗星と言う彗星が放出した塵が地球に飛び込んできたときに見られます。放出した塵は、最初は彗星のそばを彗星と同じように太陽のまわりを細長い楕円軌道を描いて移動していくのですが、ペルセ群の場合、この彗星が長い間太陽のまわりを回ってる間に塵をどんどん放出し、軌道上にまんべんなく塵をちりばめてしまったものと考えられてます。そして地球は毎年8月12日頃に、この彗星軌道の近くを通り過ぎます。このため、多くの塵が地球に飛び込んで、たくさんの流星が見られるのです。
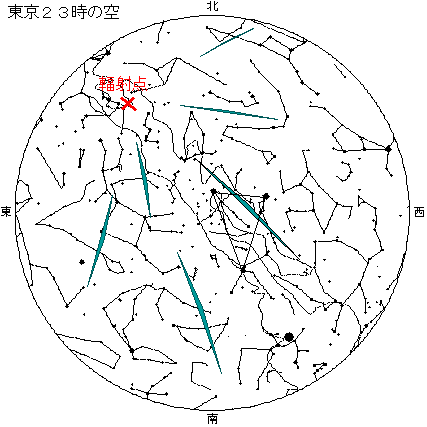 最も多く見られるのは8月12日の明け方で、天の川が見えるようなきれいな空では1時間に50個くらいと言われます。また前後日でも1時間に30個くらいは、見られそうです。明け方になるほど見やすくなります。
最も多く見られるのは8月12日の明け方で、天の川が見えるようなきれいな空では1時間に50個くらいと言われます。また前後日でも1時間に30個くらいは、見られそうです。明け方になるほど見やすくなります。
ところで、「ペルセウス座流星群」と言うのは、流れた流星の方向をたどると、ペルセウス座のある一点に集まるのでこう言われます。これを輻射点(ふくしゃてん)、または放射点(ほうしゃてん)と言います。ペルセウス座にだけ流れるのではないのです。が、この放射点が高く昇るほど、見られる流星の数は多くなります。なので23時(午後11時)頃では、明け方の3割〜半分くらいの数が見られると思います。
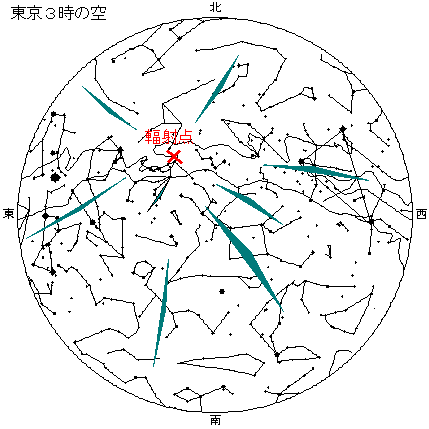 また当然、東京のように空の明るい場所では見られる数も少なくなります。府中くらいの空では半分より少な目といったくらいです。できるだけ暗い、きれいな空で見たいものですね。
また当然、東京のように空の明るい場所では見られる数も少なくなります。府中くらいの空では半分より少な目といったくらいです。できるだけ暗い、きれいな空で見たいものですね。
(星図は StellaNavigator、AstroArts/ASCII を加工して作ってあります)
天showのコーナーへ ペルセ群観測報告のページへ FASのホームページへ戻る
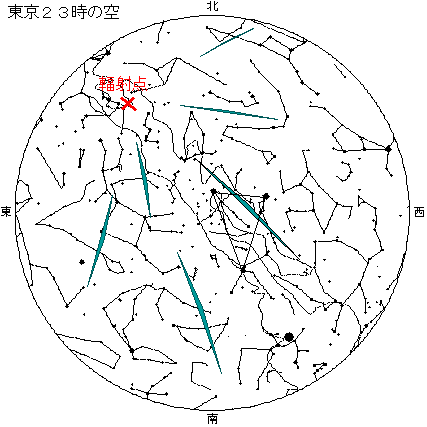 最も多く見られるのは8月12日の明け方で、天の川が見えるようなきれいな空では1時間に50個くらいと言われます。また前後日でも1時間に30個くらいは、見られそうです。明け方になるほど見やすくなります。
最も多く見られるのは8月12日の明け方で、天の川が見えるようなきれいな空では1時間に50個くらいと言われます。また前後日でも1時間に30個くらいは、見られそうです。明け方になるほど見やすくなります。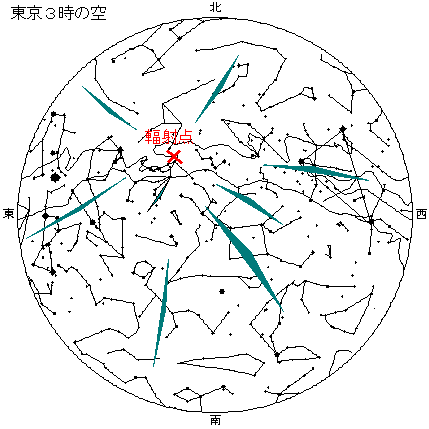 また当然、東京のように空の明るい場所では見られる数も少なくなります。府中くらいの空では半分より少な目といったくらいです。できるだけ暗い、きれいな空で見たいものですね。
また当然、東京のように空の明るい場所では見られる数も少なくなります。府中くらいの空では半分より少な目といったくらいです。できるだけ暗い、きれいな空で見たいものですね。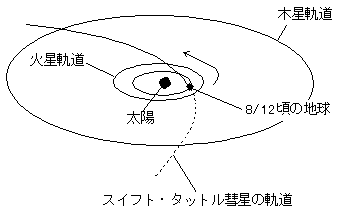 流星の正体は、彗星(ほうき星)が太陽に近づいたときに、熱で溶けて放出した塵(ちり)だと言われてます。これがたまたま地球に飛び込んできたとき、大気との摩擦で高熱になって光を放ち、流星として私たちの目にきれいな姿を見せるのです。
流星の正体は、彗星(ほうき星)が太陽に近づいたときに、熱で溶けて放出した塵(ちり)だと言われてます。これがたまたま地球に飛び込んできたとき、大気との摩擦で高熱になって光を放ち、流星として私たちの目にきれいな姿を見せるのです。