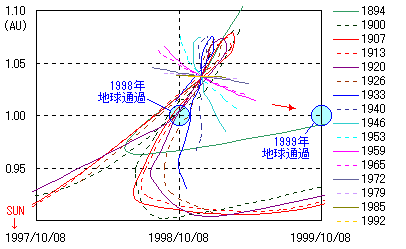
fig.1 降交点通過と位置の関係
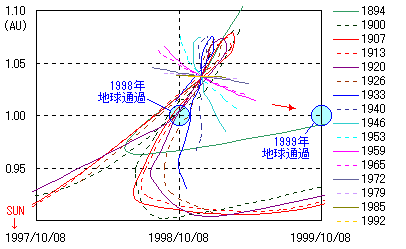
fig.1 降交点通過と位置の関係
Fig.1の通り、トレイルは木星の摂動の影響を大きく受け、複雑な様相を示している。
その中で、一部のトレイルは1998年に地球軌道付近を通過していることがうかがえた。
Table.1 1998年接近のトレイルの精細計算結果
| 放出年 | 放出速度 | 位置 | DATE | TIME(JST) | Ls(2000) | 距離Δ(AU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | +6.0m/s | 降交点 最接近 | 10/9 10/8 | 01h15m 21h20m | 195.202 195.045 | +0.0135 +0.0134 |
| 1913 | +6.7m/s | 降交点 最接近 | 10/9 10/8 | 00h22m 21h20m | 195.166 195.045 | +0.0108 +0.0107 |
| 1920 | +8.2m/s | 降交点 最接近 | 10/8 10/8 | 23h34m 21h25m | 195.133 195.049 | +0.0066 +0.0066 |
| 1926 | +10.8m/s | 降交点 最接近 | 10/8 10/8 | 22h33m 22h25m | 195.091 195.090 | +0.0004 +0.0004 |
| 1933 | +15.4m/s | 降交点 最接近 | 10/8 10/8 | 20h56m 23h35m | 195.025 195.138 | -0.0094 -0.0094 |
※降交点通過時刻は1分精度、最接近時刻は5分精度で算出
結果、最も地球に接近するトレイルは、1926年由来のトレイルであった。このトレイルの降交点を地球が通過したのは10月8日22時33分、最接近は22時25分頃(ともに日本時)であった。接近距離は+0.0004AUであった。この値は、計算誤差(0.001AU)よりも小さい。
1998年の観測結果から得られた極大は、22時10分頃(日本時)であり、その差は数十分の差で一致する。
なお、この他に1933年、1920年放出トレイルも、比較的接近することがわかった。
トレイルの実際の太さについては未検討である。ある程度の太さがあれば、これらからの流星の出現の可能性も考えられる。
概念をわかりやすくするため、アッシャー図についても、まとめた(ただし、トレイルの太さは不明のため、半径を計算誤差の0.001AUと仮定して作図した)。
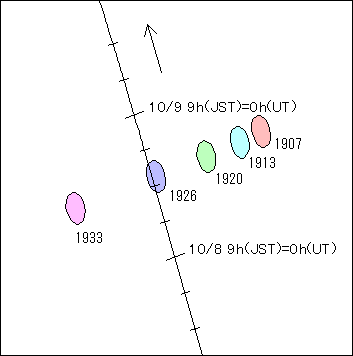
fig.2 アッシャー図によるトレイルの位置関係
Table.2 1999年接近のトレイルの精細計算結果
| 放出年 | 放出速度 | 位置 | DATE | TIME(JST) | Ls(2000) | 距離Δ(AU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | +60.0m/s | 降交点 最接近 | 10/9 10/9 | 19h48m 20h25m | 195.712 195.740 | -0.0027 -0.0026 |
| 1966 | +69.5m/s | 降交点 最接近 | 10/9 10/9 | 20h57m 21h25m | 195.760 195.782 | -0.0015 -0.0015 |
※降交点通過時刻は1分精度、最接近時刻は5分精度で算出
結果、これら2本のトレイルとは、ともに0.001〜0.003AU程度まで接近することが判明した。ただし、放出速度は+60m/sを越えており、物質の密度が小さいことがうかがえる。
実際の観測結果では、10月9日の20時頃にHR=20〜30の極大がうかがわれた。計算結果の1959年のトレイルとは、ほぼ数十分の誤差で一致するため、このトレイルに由来することが推定された。
また21時台もHRは〜10程度の出現が観察され、これが1966年のトレイルに由来する可能性も考えられる。
1998年同様、アッシャー図による位置関係を示す。
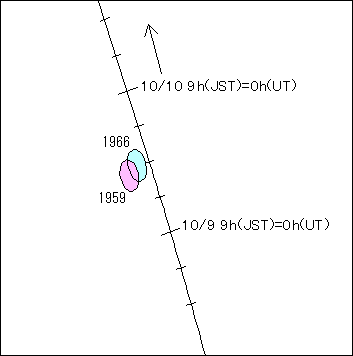
fig.3 アッシャー図によるトレイルの位置関係